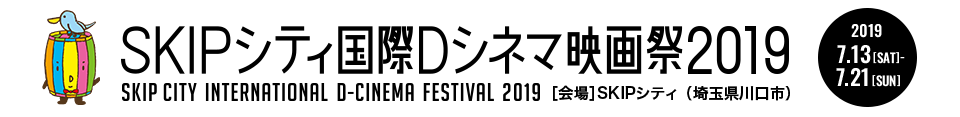ニュース
【インタビュー】国際コンペティション『旅愁』呉沁遥監督

『旅愁』
呉沁遥(ゴ・シンヨウ)監督インタビュー
——『旅愁』は、立教大学大学院映像身体学専攻の卒業修了作品。まず、立教大学大学院に進学を決めた理由を教えてください。
教授に万田邦敏さんがいたからです。万田先生に学びたくて、行く決意をしました。
——万田監督の作品のファンだった?
そうですね。以前、万田監督の映画を観て、すごく感銘を受けました。それで調べたんです。そうしたら、立教大学で先生をしていることを知りました。じゃあ「ぜひ万田先生の下で学びたい」と思い立ち、立教大学大学院を受験しました。
——万田さんの作品の魅力は?
万田監督の演出は、私には日本のスタイルとフランスのスタイルが合わさっているように感じられました。それと役者さんの演技の引き出し方も素晴らしい。そういった点をどうにかして学べないかなと思いました。
——実際にゼミに入って学んでみていかがでしたか?
すばらしい時間になりました。1番勉強になったのはやはり役者さんの扱い。どういう風に動かすのか、セリフをどういう形でいわせるかなど、どう役者の演技をコントロールしていくのかはすごく勉強になりましたね。
あと、シナリオを描きながら、1回エチュードをやって、そこで生まれたことを脚本に落とし込んでいったりといった映画作りにおいて、作品をよりよいものにするためにいろいろな手法があることを知ったのも大きかったです。
——作品は、東京で民泊を営む李風と、その近所で個展を開いていた画家の王洋の出会いから始まり、二人の距離がだんだん近くなってきたところで王洋の元カノ、ジェニーが出現することで、男女3人のいびつな三角関係が描かれます。
もともとは万田先生の授業の課題で「三角関係」についての短編を作りました。ただ、そのとき、私は日本にきてまだ日が浅く、日本語もまだまだで、日本の役者さんに自分の意図やこうした演技をしてほしいといった指示がほとんどできませんでした。結果的に、すごく悔いが残って、きちんとコミュニケーションの図れる中国のキャストでもう一度、「三角関係」についての作品をやりたい気持ちがありました。同時にこれまで自分の体験してきたことや通過してきたことでないと完全に物語も掌握できないなと思って。「⽇本にいる自分と同年代、20代の中国人の若者たちの三角関係を描こうと」と⽬標を切り替えて、シナリオを書いていきました。
——どのようにしてシナリオにまとまっていったのでしょう?
まず、私自身が民泊を利用して旅行することが多く、周りに民泊を経営する友人もいたことから、いろいろと話を聞けたこともあって、李風という主人公が決まりました。そこから万田先生の指導に従い、試しにエチュードを行って、話を膨らませていきました。
その間、日本にいる中国の知り合いや友人をリサーチして、異国での生活や日本社会への戸惑い、20代の若者としての悩みや将来の迷い、恋愛観みたいなことも聞いて、ひとつにまとめていきました。

『旅愁』場面写真 ©旅愁2019
——異国で生きることの寂しさや居場所のなさ、日本で生きることへの本音と建て前といったことも描かれていて、日本人として気づかされることも多々ありました。
いろいろとリサーチして、中国の留学生たちが日本で感じるさまざまなことをなるべく正直に出しているところはあると思います。
——一方で、三角関係に象徴されているように男女間の恋愛についてかなり踏み込んだ内容になっていると思いました。
「恋愛」というか「愛」というのは、自分の中でずっと答えの出ていないひとつの大きなテーマです。いつからか「ほんとうの愛」とは何か、考えるようになりました。
たとえば劇中で李風は王洋に想いを寄せる。一方でジェニーは別れても王洋にまだ未練がある。王洋はどっちつかずで恋愛にあまり興味がない。
この関係が示しているように、私は恋愛はどのような形があってもいい。男女間でも男性同士でも、女性同士でも成り立つ。いかなる状況でも、どんな困難な状況であろうとも結びつくのがTrue Loveではないかと思うんです。そこには性別とか育った環境とか家柄とか関係ない。
LGBTの存在がこれだけ世界に浸透しているのに、いまだに社会は恋愛に対して旧態依然としているというか。男と女のみの性別で線引きしようとしている気がする。なので、この作品の中で、「愛」を描くことはひとつの大きなテーマでした。
——作品を拝見すると、たとえばボーイズラブ系の映画なども興味があるのかなと思いました。
そうですね。さまざま恋愛を知るということで興味があります。その分野に挑戦したい気持ちもあります。
——出演した俳優さんたちはみなさん素人ということですね?大変だったのでは?
素人とプロの役者に対する演出は違ってきます。ただ、そのことは最初からわかっていたこと。なので、私は演じてくれる人たちに役に寄せてもらうよりは、役に、彼ら自身の実際の性格や人間性をどんどん入れていくことにしました。そうすれば演じやすくなるだろうし、無理をしいることにもならない。実際、いい形になったと思います。
——初の長編映画を完成させたわけですが、そもそも最初に映画を作ってみたいと思ったきっかけは?
高校のとき、学校がすごくつまらなくて(笑)、映画を観ることが唯一の楽しみでした。それで、知人と映画を作ってみたら、すごく楽しくて、それからずっと映画制作のことばかりを考えるようになしました。
それで、大学に進んで映像制作について学びました。ただ、そこのカリキュラムとしては映画よりもテレビ寄りで。ドキュメンタリーやちょっとした番組を作りました。ただ、学んでみて最後に思ったのは、テレビよりも私は映画が好きということ。これで自分の本心に気づいて、立教大学大学院の門を叩きました。
——じゃあ、すでに映像制作のノウハウは中国の大学で学ばれていたんですね。こうした経緯を経ての、今回は念願の映画だったと。
そうです。自分にとって『旅愁』はやっと作ることのできた映画です。
——今回、国際コンペティション部門に選出されたのは、うれしかったのでは?
ラッキーと思いました。ただ、ほかの作品をみると、すごい作品ばかりなので、自分の作品がここに並んでいいものかと戸惑っています。韓国の有名な俳優のキム・ユンソクさんの監督作品と自分の映画が一緒に並んでいのはなんだか不思議な気分です。
——キム・ユンソク監督は来日予定です。
出演作は観たことがあるので、もし会えたらすごくうれしいです。
——映画祭で楽しみにしていることはありますか?
やはり、このような大きな会場で自分の映画が観ていただけるのは楽しみです。でも、一方でどんな反応があるのか、期待と不安が半々といったところもあります。
——現在は中国に戻られて、どのような活動を?
今はCMなどの映像制作をしています。映画をまた作りたいので、その資金を作ろうと頑張っています。
——どんな作品を作っていきたいと思っていますか?
この社会の片隅で生きているような市井の人々に焦点を当てた映画を作っていきたいです。今を懸命に生きている人々の息遣いや本心が伝わる映画が作れたらと思っています。
(取材・文:水上賢治)