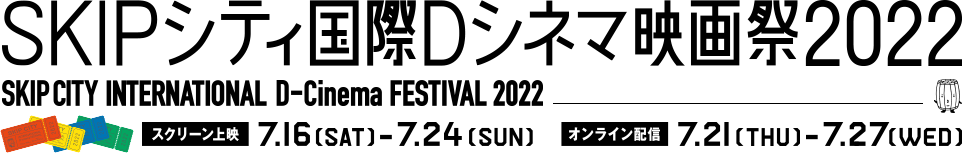ニュース
【インタビュー】国内コンペティション長編部門『Journey』霧生笙吾監督

――『Journey』は、武蔵野美術大学造形学部映像学科の卒業制作作品になります。スタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』をはじめとしたひとつの哲学が根底に流れている独創的なSF映画になっていることに驚かされるのですが、どういう発想から生まれたのでしょう?
僕は武蔵野美術大学で小口詩子教授のゼミに入ったのですが、そこで、ひとつ大きな課題を出されました。それは100プランといって、4年生の前期の間に作品を作るための100個のアイデアを考える、それをもとに卒業制作を作るというものでした。
毎週20個、5週間かけて100個のアイデアを出すというのが前期の主な作業だったのですが、僕はSF映画を作りたいと思っていたので、勝手に自分でしばりをつけてSFに関することで100個のアイデアを出すことにしたんです。ここで出したアイデアをもとに『Journey』の脚本作りはスタートしました。
――当初からSF映画を考えていた?
そうですね。小学生のときに映画にどっぷりとはまったのですが、きっかけはSF映画でした。いまもほかのジャンルよりもSF映画をみるときの方がが気持ちが高揚する自分がいます。なので、卒業制作はSF映画と決めていました。
――どういうアイデアの種が集まってこのストーリーができていったのでしょう?
けっこう、はじめに思いついたアイデアが最後まで残る形になりました。たとえば、宇宙に取り残されてしまった老人の存在とか、そこにやってくるロボットとか。
――この作品の核となっている、人が肉体から意識を切り離し、意識だけで存在し続けることができるという設定も当初からのアイデアだったのでしょうか?
それについては、大学4年になる前からうっすらと考えていたことでした。まったく別で、人間がある年齢に達したら意識だけを人工に作られた肉体に移すことができて永遠に存在することができる。そのような世界になった近未来で、使い捨てられる運命の肉体として生まれた女性に、300年間、肉体を変えながら生き続けている男が恋をするという物語を考えていたんです。これはこれで1本の映画になるかなと考えていたのですが、今回脚本を進めていく中で、意識の要素をこちらでも使おうという考えに至りました。
作品は、肉体から意識を解放することが可能となった近未来が舞台。宇宙飛行士になることをあきらめ地球で働く慶次と、心を病み、意識のみの存在に憧れを抱き始める妻の静の関係の変化を主軸に、「生きることの意味」「死」といった問いが投げかけるひじょうに深い物語が三部形式で描かれていきます。
――トリロジーということでひとつひとつについて聞きたいのですが、まず作品の全体像で考えていたことはあったのでしょか?
全体像としては、テレンス・マリック監督の『ツリー・オブ・ライフ』を参考にしたところがあります。この作品に限らず、彼の作品は、たとえばベトナム戦争のひとりの兵士とか、個人の話からはじまりながら、それが宇宙や生命、人類の営みといった非常に壮大で想像をめぐらす世界へとつながっていく。
自分はこの世の中で小さな存在に過ぎない。でも、この世界に存在して、この宇宙に存在している。そんなことが感じられるのが好きなんです。ですから、『Journey』に関しても、宇宙は果てしないし、地球も世界も広い。でも、自分はこの世界に、この宇宙に存在していてつながっている。そうしたことを感じられる映画にしたいと考えました。
――では、序章となる、第一部ではどういうことを考えたのでしょうか? ここでは慶次と静の日常の生活と、なにか未来に対しての二人の考えの不一致が描かれます。
SFというとなにかと壮大な世界になりがちなのですが、そうではなくここでは個人の、それもきわめて一般の人々の話にフォーカスしたいと思いました。潤沢な予算があるわけではないので、ビジュアル的なインパクトのある映像でこの近未来の世界を可視化してみせていくことは難しい。
そのかわりというわけではないですけど、こういう時代を迎えた人間の心模様をきちんと描こうと思いました。慶次と静という夫婦であり、男女でもある二人が、意識で存在することが可能になった世界でどう生きていくのか、どういう人生の選択をしていくのか、個人レベルで考えていることを丹念に描こうと思いました。
――第二部は、意識のとらえ方かたをめぐって、慶次と静の間に微妙なずれが生じる。この章は、あまり明かすことができないのですが、夫婦の物語、意識内意識の世界など、いろいろな解釈が成り立つものになっています。
二部をどういうものにするのかは、けっこう迷いました。最終的には、静の存在そのものに焦点をあてて、いろいろな解釈ができるものになりました。
――そして、第三部は、その先の世界、もはや人が限りなく存在していない世界が描かれます。
裏を明かすと、アンドレイ・タルコフスキー監督の『ストーカー』のようなことができないかと考えました。ここもあまり明かせないですけど、人が未知の領域に足を踏み込んでしまう。そこで、彼らが人の滞在的な意識の中にある共通のものを感じる。
そういうことを描くことで、たとえば生命の鼓動のようなものを感じられるものになればなと考えました。
――「生」と「死」、とりわけ「死後」ということも作品に流れるひとつのテーマではないかと感じました。
「死んだあと、自分はどうなってしまうんだろう?」と、小学生のときに考えたことをいまでも明確に覚えています。そのとき、父に訊いたんです。「死んだら、僕はどうなっちゃうの?」と。父には「どうなるんだろうね」と答えを濁されて、「なんだ知らないのかよ」と思ったんですけど、そのとき、自分としてはすごく不安になって「生き続けたい」という思いにかられた。
一方で、月日を重ねる中で、自分の存在意義を見失う瞬間や、なぜ生きねばならぬのか?といったことを考えるときもあった。そのあたりの自分の考えてきたことが作品に封じ込まれたのかなと思います。
そう考えると、小学生のときの父への問いがこの作品の根源になっているのかもしれません。
――その物語の舞台になる場所ですが、非常にに近未来と感じられるしかるべきスペースを選んで撮られていると感じました。
実は、中心になっているのは母校の武蔵野美術大学の学内なんですよ。いや、卒業制作でもう卒業するし、利用できるだけ利用し倒そうとおもって(笑)、ふだんから使えそうな場所にめぼしをつけていたんです。
慶次が清掃の仕事をするあのコンクリートの場所は、実は学生食堂からみえるところにあって、ずっと「使えるな」と思っていました。あと、慶次が尋問を受けるあのスピーカーの場面の場所も、学内にある、吹き抜けになっている階段の踊り場のようなところで吹き抜けになっている。そこで暗幕をはって、あのように暗くして撮影したんです。
この撮影がけっこう大変で、常にライトがついている上、吹き抜けなので外部からの外光も入ってくる。その光をすべて遮断しなければならなくて、暗幕を3Dのように立体的に張ることになったんですけど、これがものすごく時間がかかって大変でした(苦笑)。
――おそらくSF映画を作ることが一つの目標だったと思うのですが、作り終えてどんなことを感じましたか?
大学で上映する機会が何度かあり、客観的にみることができたのですが、やはり粗ばかりが気になります。もっとできることがあったのではないかと反省することが多々なのですが、大学に入学したとき、卒業制作で宇宙を描くとはまったく思っていませんでした。
SF映画は無理だろうという気持ちがどこかにあった。それを考えると、ひとつの目標としていた到達点まではいけたのかなと思っています。ただ、いま言ったように課題も山積状態で。まだまだ演出力や脚本力に磨きをかけないといけないと痛感しました。
最近も何本か脚本を書いたんですけど、会話のかけあいみたいなところが苦手で、その人物像の魅力が欠けてしまうところがある。『Journey』は、SFということでちょっと無機質で機械的な堅い感じの会話や言葉遣いを意識したところがあった。ただ、そうしたのは、ふつうの魅力的な会話のやりとりを自分が書けないことの裏返しだったのではないかと最近感じています。
なので、満足はしていない。でも、自分としては念願のSF映画に踏み出すことができた作品で、しかもこのように映画祭に入選することができてひとつ自信になりました。

©霧生笙吾
――ここからは映画監督の道を志すに至った経緯を少しお聞きできればと。プロフィールを拝見すると、武蔵野美術大学に進んで、はじめは写真などのアートワークから始めたということですが?
まず、高校までいわゆる進学校に通っていて、来たる大学受験に向けて勉強に明け暮れていました。ただ、思ったように成績が延びなかったプラス、正直、志望校に進んだところで先がみえないというか。希望の大学に受かったとしても、その先やっていくことに自分が熱意をもって取り組めるのか、まったく見出せなかった。
そのとき、やはり自分の目指す道へ進まないとと考えたときに、映画をが作りたい気持ちがあることに気づきました。父親がSF映画が好きで、小学生のころから、TSUTAYAでレンタルしてきた映画を毎日みるような生活を送っていました。父の影響で僕もSFが好きになって、そのうちにほかのジャンルも観るようになって、いつか作ってみたいなと思っていて。
そのことをが進路を決めないといけないときに、思い出した。それで、浪人をして、広い範囲の映像制作が学べるということで武蔵野美術大学へ進みました。
――では、大学入学前から映画監督を目指していた?
そうですね、作り方とかまったく知らなかったですけど、映画を作りたくて武蔵野美術大学に進みました。はじめアートワークからはじめたのは、そもそも1年と2年のカリキュラムがそうした映像や写真といったアートワークが中心のカリキュラムなんです。ただ、2年生の前期の授業で必修で実写映画の授業があったので、それを経て、後期になにか映画が撮れればと思っていたんです。
ところが必修科目ということで全員とらないといけないので、映画以外のアーティストを目指している人もいるわけで、誰が実写に興味があって映画を作りたいのかわからない。それでもなんとか撮影までこぎつけたんですけど、やはり映画に興味のないメンバーもいてうまくいかなくて、心が折れて断念したんです。
その後、3年でデジタルドラマを撮る授業があったのですが、それは実写に興味のある人たちだけが集まっていて、そこでようやく1本映像作品を撮ることができた。その後、進級作品でもう1本作品を作ったんですけど、それは撮影をはじめ基本的にほぼ自分ひとりでやって、作品自体は求めるものができた。ただ、現場が失敗してしまった。
やはりカメラもやって監督もやってだと、指示が行き届かなくて、スタッフも俳優も変な待ち時間ができてだれてしまう。スケジュール管理も散漫になってしまい、信頼を失い、気づいたら自分が演出するときは蚊帳の外みたいな状態にまでなってしまった。この失敗を改善して、卒業制作の『Journey』に取り組んだという流れです。
――影響を受けた監督や作品は?
いっぱいいますね。ただ、一番好きな映画は決まっていて『ブレードランナー』です。小学校4年生で初めて観たんですけど、そのとき暗いし、雨降っているし、『なんなんだこれは?』となにがなんだかわからなかった。
当時、僕は『スター・ウォーズ』的なものを求めていたので、なんとも腑に落ちない。そのとき、父親に「まあ、わかるときがいつかくるよ」と言われたんですけど、「なんだよそれ」と思っていた。ところが、高校から予備校に通っているとき、大学と何度も見直していくうちに、「こういうことだったのか」とその都度、発見がある。こちらに思考させる余地がいたるところにある。こちらが類推した先に、また別の世界がみえてくる。こういうことが映画的というのかなと思います。
あと、アンドレイ・タルコフスキー監督の作品も好きです。見るたびに退屈なカットで眠気に襲われるんですけど、時間をそのまま描写している感じがして。その描くものに対する誠実さが好きです。
――では、今回の入選をどう受けとめていますか?
入選のメールが届いたときは、落選を伝えるものだと思っていました。ちょうど、英会話教室の申し込みをしにいって、そのテストを受けている最中にメールが入っていて。その結果待ちのときに、確認したんですけど、ほんとうに入選していると思えなくて、5回ぐらいきちんと文面を読み直しました(笑)。
素直にうれしかったです。昨年、2つ作品を作って、いろいろな映画祭に出したんですけど、一次審査や最終選考に残ったものの入選には至りませんでした。一番最初に作ったものだから、上々かなと思っていたんですけど、同期が何人か入選して、めちゃくちゃ悔しかった。だから、すごくうれしいし、自分も「映画を作っています」と言えるようになったかなと思っています。
『Journey』作品詳細
取材・写真・文:水上賢治