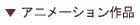『Noise』 松本優作監督インタビュー

――長編初監督作品となった『Noise』ですが、秋葉原無差別殺人事件が物語の大きな背景に据えてあります。
高校一年のとき、中学時代の同級生が亡くなりました。自殺です。実は、その直前に、彼女から僕の携帯にメールが入っていました。でも、返信しそびれてしまい……。さらにそのままにしてしまいました。そのため、実際に彼女の死を知ったのは、亡くなってから一年後ぐらい。すぐにお墓参りにと思ったんですけど、すでにご家族は引っ越されていて、それも叶いませんでした。どこか心の整理がつかないまま時間を過ごしていたとき、秋葉原の事件が起きたんです。このとき、僕の中で彼女の死と秋葉原の事件がどこか重なり、無関係とは思えませんでした。命を奪う行為が彼女は自らに向かったけど、秋葉原の犯人は他者へと向かった。Yの字で表すなら、最後は二手に分かれたけど、そこへいきつく過程は紙一重で、どっちに転んでもおかしくないんじゃないかなと。そのとき、そうなってしまう理由を、自分なりに考察したい気持ちが芽生えました。
――では、構想自体はずっと温めてきた?
そうですね。10代のころから、いつか形にしたい気持ちはありました。脚本自体も専門学校に通っていたころから、こつこつと書き続けていました。実際に学校の卒業制作で今回の映画の元となる短編映画も制作しました。学生を経て、社会に出て働きだしたわけですけど、このテーマに一度きちんと向き合わないと、自分自身、なにか次のステップに進めない気がしていました。
――長年温めてきて、作品制作へ踏み出せたきっかけは?
専門学校を卒業後、テレビやCMなどを作っている小さな制作プロダクションで働きながら、やがてフリーになってキャリアを積んでいきました。その中で、ある仕事でアイドルオーディションをすることになったんですけど、そのとき、今回、主演を務めてもらった篠崎こころさんが来ていました。篠崎さんを見たとき、亡くなった彼女の姿が重なったんです。それですぐに篠崎さんに打診しました。“自主ですけど、一緒に映画を作りませんか?”と。そこから『Noise』はスタートしました。
――物語は秋葉原無差別殺人事件から8年後が舞台。事件で母を失った地下アイドルの女の子、父との関係がうまくいかず秋葉原に毎日のように足を運ぶ女子高生、母親に裏切られ、やるせない怒りを誰にもぶつけることができない青年らの心の葛藤と苦悩が描かれていきます。どの人物もその心情が伝わってくるのですが、キャストのみなさんにはどんな演出をしたのでしょうか?
これは恵まれたことだと思うんですけど、役者さんみなさんがその役にご自身の何かを投影してくれて体現してくれた結果だと思います。たとえば、主演の篠崎さんですけど、最初に彼女を見て書いた脚本を手渡したら、こう返ってきました。“演じる役の女の子は母親を亡くしているけど、それ以外は自分も同じようなことしてきた”と。それならばと篠崎さんの人生に沿って役を肉付けしていきました。山本里恵役の安城うららさんも同じです。
そして、何と言っても撮影監督兼出演をしていただいた岸建太朗さん。映画の演出だけでなく、色々な素晴らしいアドバイスをたくさんしていただきました。岸さんがいなければ映画を完成させることはできなかったと思います。また、大橋健役を演じてくれた鈴木宏侑さんには撮影一ヶ月前から、実際に映画の中で健が住む家に住んでいただき、役作りをしていただきました。家の美術なども、実際に役者自身がそこに住み、生活をしていく上で出てくるゴミや服などがリアルな嘘ものではない美術となりました。
――物語の中では秋葉原以外の事件にも目を向けています。
もともと秋葉原の事件だけを描きたかったわけではありません。むしろいろいろな視点から多角的に見ることで、事件の本質にはじめて迫れると思いました。被害者目線、加害者の目線、事件に関係しない人の目線も必要だと思いましたし、同時に過去に起きた同様の無差別殺人事件にも目を向けないといけないと思いました。そこで自分なりに調べていくと、池袋でも同様の事件が起きていることに突き当たりました。この事件の犯人は親に捨てられ行き場を失っていき犯行に及ぶ。あと、中上健次を信望していて「十九歳の地図」の一説を書いたメモを手にしていた。そして、奇しくも「十九歳の地図」は、連続殺人犯の永山則夫がひとつのモチーフになっている。そういうリンクがあったので、大橋健という青年の役には、これらの要素をすべて背負ってもらうことで、過去にまでさかのぼってこうした事件について考えられればいいなと思いました。
――自身の中で一度は向き合わないといけない題材に取り組んでいかがでしたか?
正直なことを言うと、なにか答えが見つかるかなと思っていたんですけど、見つかりませんでした。ただ、作品を作ったことで、自分自身の中で彼女の死についてひとつ区切りをつけられた気がします。これからも常にどこかで記憶が甦ることではあると思うのですが。また、今回僕たちが映画作りを通してやってきた、事件をたくさんの視点から想像し考えること。こういった行為こそが、答えを見つけることよりも大切なんじゃないかなと思いました。
――プロフィール的なところを聞きたいのですが、監督を目指したきっかけは?
中学生ぐらいのとき、ほんとうに家から出なくて(苦笑)。映画ばかり観ていたんです。たまたま海外ドラマの「プリズン・ブレイク」のメイキングを観たとき、“これやりたい”って思っちゃったんです。そこから映画は楽しむのではなくて作る目線で見るようになりました。それで映画の専門学校に進んで、8ミリで撮った短編映画が先生に褒められて、“これいける!”と勝手に勘違いしちゃって(笑)、今に至っています。
――21歳のとき、DVDシネマ『彼女が彼女を愛した時』を手掛けられています。
制作会社で働いているとき、ADからちょっとディレクター的な仕事も任せていただけるようになったころ、お話しをいただいて手掛けました。
――今回の『Noise』とはずいぶん違うタイプの作品だと思うのですが?
そうですね。ただ、自分として作っていきたいのはやはり、今回のような社会性やメッセージのあるものですね。よく周りの知人とも話すんですよ。“映画をやっている人はあまり幸福な人生を送っていないよね”って(笑)。そういうなにか鬱屈したものやたまったものを吐き出せるのが映画なのかなと現時点で自分は思っています。自分が実際に体験したことじゃないと今の僕はおそらく映画にできないですね。
――今回のコンペティション選出の率直な感想を。
素直にうれしかったです。よくぞ、“見つけてくれた”と(笑)。実は、僕にとってSKIPシティ国際Dシネマ映画祭は、一番親近感のある映画祭です。去年も普通に見に来ていました。そういうこともあって、“自分の作品がここで上映されたら”と思っていました。その中で、いろいろな人に見てもらえる機会がまず出来たことは大きいです。今回、メインテーマと劇中音楽をbanvoxさんに担当していただいたのですが、banvoxさんと映画についてセッションを繰り返しながら楽曲制作をしていただきました。なので音楽的な視点からも見ていただきたいです。どういう感想をいただけるのか今から楽しみです。
――初監督作品を作り終えたばかりですが、これからなにか考えているプランはありますか?
最近、フィリピンと日本のハーフの知人とよく話すのですが、フィリピンのことを聞くとすごく興味深い。それから、経済の発展がある一方で、貧富の差がさらに広がっていたりと、東南アジアの状況についてのニュースをここのところけっこう目にしますよね。そんなこともあって、具体的なプランがあるわけではないのですが、いま、東南アジアでひとつ映画を作ってみたい気持ちがあります。
あと、夢は大きくということで、ハリウッドに行ってみたいですね。ただ、それよりもなによりも、枠にとらわれずに自分なりの映画作りをこれからも続けていけたらと思っています。資金はプロデューサーに任せてという人がほとんどなのでしょうけど、僕自身は今回がすごくいい形で作品作りに臨めたので、次回も資金集めからやってみたい。それで実績を積んで、大きく成長していけたらと思っています。
(文・写真:水上賢治)
・『三尺魂』 加藤悦生監督インタビュー
・『ひかりのたび』 澤田サンダー監督インタビュー
・『Noise』 松本優作監督インタビュー