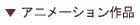『三尺魂』 加藤悦生監督インタビュー

――前作『PLASTIC CRIME』に続いてのコンペティションのノミネートになりました
前作の初監督作品『PLASTIC CRIME』は、もう3年前になりますけど、おかげさまでSKIPシティ国際Dシネマ映画祭2014にノミネートされて、多くの方に観ていただくことができました。ただ、スタッフとキャスト、ほんとうにみんな頑張ってくれたので、自分としてはもっと多くの人に届けたいなと。それで映画祭上映後も、劇場公開できないか模索していたんですけど、なかなかうまくいかなくて……。
まだ、上映のチャンスを諦めてはいないんですけど、それだけに奔走しているわけにもいかない。映画祭から一年ほど経ったぐらいから、次の脚本を書き始めました。それで一本書き上げて、もう具体的にやろうという直前ぐらいまで話が進んで昨年のSKIPシティに応募を考えた作品があったんです。
でも、その間に、SKIPシティのオープニング作品の脚本募集があり、もう一本書き上げた脚本が今回の『三尺魂』でした。残念ながら落選してしまったんですけど、自分としてはいい脚本が書けた感触があったので、これを形にしたい気持ちが日増しに強くなって(笑)。先ほど触れたもう一本の撮影寸前までいっていたのをいったんなしにして、先に『三尺魂』を撮ることにしました。
スタッフには迷惑をかける形になって申し訳なかったのですが、みんなも僕の熱量が『三尺魂』に傾いていたことに気づいていたみたいで(笑)、最後は納得してくれました。
――前作の『PLASTIC CRIME』は引きこもりの青年を主人公にしたユニークな犯罪劇。今回の『三尺魂』もまた、集団自殺というシリアスな題材をバックにしながら、人情味あふれるヒューマン・ドラマに仕上がっています。この発想はどこから生まれたのでしょう?
ここで“今の社会について僕は…”とか言えたら映画作家っぽくってカッコイイんでしょうけど(笑)、全然そんなことはなくて。僕はふだん、テレビのディレクターをしているので、たとえば今回であったら募集要項から考えてしまう。ですから、今回だったら予算限られているからワンシチュエーション、密室劇だったらいけるなとまず決まって(笑)。次にオープニング作品なら誰でも楽しめるものがいいんじゃないかと。それで誰もが楽しめて大好きな映画で思いついたのが『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(笑)。それでじゃあタイムリープものにしてみようとなって、組み合わせていったら、こんなストーリーができた感じです。
――集団自殺、それを花火を使ってするという発想がもう異色といっていいかもしれません。
これも偶然の産物。単純にオープニング作品なので、しめっぽくなるのはよくない。華々しく賑やかに飾れるものがいいよねと勝手に自分は思って、“打ち上げ花火いいじゃん”と(苦笑)。それで結びついちゃったんですよね。ほんとうに深い意味がなくてすいません。
――物語は、とある山小屋に集団自殺を考えた男女4人が集まります。でも、なぜか爆発するたびに集合前の時間に戻ってしまう。そのたびに、まだ将来のある女子高生を、ほかの大人の3人が諭して自殺を思いとどまらせようとしていきます。この現実と非現実を往来するような構成がまずユニークでした。
集団自殺を喜劇的に扱うと不謹慎に受け止められるかもしれません。ただ、僕の中では、まずいろいろな死があるけど、死は誰もが絶対に避けられないものと考えがありました。そして一方で、タイムリープ=時間を繰り返すことは絶対ないこととの考えがあって、この二つの次元を往来したら、人の本音や本心が意外と浮かびあがる気がしたんです。
あと、単純に監督としての自分の力量も試したい気持ちがありました。タイムリープは、観客のみなさんに“そんなわけないよ”と思われちゃったら、その時点でアウト。演出の力不足だと思うんですけど、逆にその世界に引き込めたら演出家としては勝ち。そこには一度チャレンジしたい気持ちがありました。自分自身はうまくいったなと思っているのですが、観客のみなさんは果たしてどうでしょう(笑)。
――ほかにこのシリアスな題材をユーモアあふれる作品にするためにした創意工夫はありますか?
脚本を書いている最中は、ずっと『スティーブ・ジョブス』を参考にしていました。近年、僕が見た映画の中で、このアーロン・ソーキンの脚本はピカ一で、BGVのように書いている間、流していました。影響を受けたかはわからないんですけど。
あと、画に関してはとことんこだわろうと当初から考えていました。ワンシチュエーションなので、とにかく撮り方はやれることを全部やって飽きさせないものにしようと。爆破は計7回あるんですけど、それぞれテーマをもってやりました。一、二回目は、デヴィッド・フィンチャーの作品のようなイメージ。画面レイアウトもカメラワークもキメキメでかっちり撮っていく。3回目ぐらいからはタイムリープの繰り返しの滑稽さが入ってくるので、躍動感ある映像にしたいいうことでナ・ホンジン監督の『チェイサー』や『哀しき獣』のようなスタイルにしようと。なので、撮影監督のイ・ソンジェのカメラワークを意識したガンガンぶれる映像になっています。そのあと以降は、ドラマが収束に向かっていくので客観性が大切。ということで、それこそカメラマン及びカメラの存在さえ感じられない同一のポジションからの映像を入れ、ここからは序盤のサスペンス風の見せ方から、物語を客観的な見せ方に変化させています。こんな風に自分たちなりに試行錯誤しながら可能なチャレンジをしていきました。
――もう一方で、凄まじい会話劇だとも思います。
会話劇として成立したのは、花火師役を演じてくださった津田寛治さんのおかげだと思います。津田さんが率先して座長の役割を担ってくださいました。津田さんが村上さん、木ノ本さん、辻さんに声をかけて、あらゆる待ち時間を使って常に4人でセリフ合わせ、リハーサルを繰り返してくださっていた。だから、準備が終わって本番のころには、ほんとうに4人の芝居ができあがっていた。小屋という狭い空間だった1カメでしか撮れない。よって、アングルを変えて何度も同じシーンを撮るんですけど、もう4人の世界が出来上がっているから何度やっても芝居が崩れないし、熱量も変わらない。これにはほんとうに助かりました。まあ、みなさん、“どんだけ同じシーンを撮るんだよ”という顔はしてましたけどね(苦笑)。あと、順撮りでやったんです。それが結果的に、村上穂乃佳さん演じる女子高生役の心と、村上さんの役者としての成長がうまいぐあいにリンクして。最初はどこか影の薄い女の子でしかなかったのが、最後は見違えるようなすばらしいヒロインになってくれた。この選択もうまくいった要因だと思います。
――そして、集団自殺から始まったドラマは、意外や意外、感動のハッピーエンディングへと向かっていきます。
まあ、そもそもオープニング作品を目指していたので、ハッピーエンド以外は考えられませんよね(笑)。映画祭の幕開けを飾るオープニング作品で、みなさんをどんよりした気持ちにさせちゃまずいですから。その中で、僕がひとつ伝えたかったのは、“人はひとりでは生きていけない”ということ。当たり前のことかもしれないけど、このことはしばしば忘れがち。人は誰かの手を必ず借りていて、誰かに助けられている。同時に自分も誰かに手を差し伸べて、誰かの力になっているときがある。そのことを忘れちゃいけない。まだ、出会っていないそういう存在がいるかもしれない。そんなことを感じてもらえたらうれしいですね。
――今回は2度目のコンペになります。
SKIPシティにはものすごく感謝しています。まず、『PLASTIC CRIME』が選出されていなかったら、今回の『三尺魂』も作っていなかったと思います。僕はけっこう諦めが早いほうなので、『PLASTIC CRIME』がノーリアクションだったら、おそらくそこで映画作りは辞めていた。SKIPシティ国際Dシネマ映画祭にノミネートされたから、まだ諦めないでやれているところがある。なんかおべんちゃらみたいになってしまうかもしれないですが、今回もノミネートされたほんとうにうれしいです。
――今回の上映で期待することは?
いや、90分楽しんでもらえたら、それだけでうれしいです。
(文・写真:水上賢治)
・『三尺魂』 加藤悦生監督インタビュー
・『ひかりのたび』 澤田サンダー監督インタビュー
・『Noise』 松本優作監督インタビュー