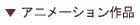『ひかりのたび』 澤田サンダー監督インタビュー

――プロフィールを拝見すると異色といいますか、まず、不動産業や商社でのクレーム処理といった会社務めの経験がある。傍から見ると、そこから一転して、現在は現代美術と映画を横断するような形で活動されているように映るのですが?
もともとテレビ業界を目指していて、10代のころから、シナリオセンターに通っていました。ただ、2000年の前後、プロの作家集団に入って企画開発などやろうという段階に入ったとき、当時のテレビは自分に合わないと判断して、一度、書くことを辞めました。
――なぜ、テレビに自分は向かないと?
当時はF1マーケティングが全盛で。まず、なにより20~34歳の女性をターゲットにしてCMや番組などのモノを書くことが求められた。そうした足枷があるうえ、最初から出しての分かり易さが求められた。たとえばある商品を紹介するとして、僕は最終的には皆にいいものと説得する自信はある。ただ、そこにいくために嫌な面を出して、わからせていくタイプ。当時は、それではダメだった。もしかしたらいまもテレビはそうかもしれないですけど。当時、講師の先生にも同世代の支持してくれる製作者やプロデューサーが出てくるまでなにもしないほうがいいんじゃないかとはっきり言われました。ちょっと反発しましたけど、客観的に見て、自分はおもしろいセリフが書けるわけでもないし、技術があるわけでもない。話やネタには自信があったんですけど、それがテレビ的ではなかった(笑)。
あと、当時は、オウムの地下鉄サリン事件などがあって、テレビと社会が自主規制を始めたころ。テレビが何か新たなチャレンジをしてなにかムーブメントを生み出すような時代が終わっていて。なんとなく安全圏の番組を作っては大失敗して、テレビが活力を失いつつあるときでした。そういうタイミングの悪いことがいろいろ重なり、自分としては、いったん作家としての活動はあきらめました。
――それからは会社員として働いていたと?
ええ。2010年に東京藝術大学大学院映像研究科に入るまでは、脚本を書くことはありませんでした。ただ、振り返ると、この間、不良債権の処理だとか、ヤクザ相手のクレーム処理の仕事とか泥臭い仕事をしてましたけど、それもネタ探しというか。“物書きは普通の人生を歩んでいてはダメ”という固定観念があって、いつかシナリオを書くためのベースを築こうとしていた気がします。そのせいで、線路に突き落とされそうになったことが3回ぐらいありますけどね。まあ、いまとなってはいい思い出です。
――2007年に発表した絵本「幼なじみのバッキー」で岡本太郎現代芸術賞に入選されていますが?
これはもうたまたまで、僕は5秒ぐらいで物語がパッと浮かぶんですけど、「幼なじみのバッキー」もそうで。友だちにメールをうっているときに、暴力と性欲が大人になる過程で、人間の人生にどう作用するのかを15分ぐらいで子どもに教える絵本というのを思いついた。で、当時、エディターズスクールに通っていて、実習でインデザインを使ってくれと言われたので、それで冊子を作って、下ネタと暴力満載の話なんですけど、子ども向けの本を出している出版社に持ち込んだんです。案の定、OKなど出るはずもなく、ある出版社からは“死ね”ともいわれました(苦笑)。
ただ、路上でよく手相を見てもらうんですけど、その占い師が、これは絵画の手相だからそういったしかるべきところに送ったほうがいいといわれて。帰宅してググったら岡本太郎賞が募集していて、送ったらなんかうまいこと入選したんです。岡本太郎美術館で展示中に小学生を中心に40冊くらい無断で持っていかれました。修学旅行で来ていた小学校の担任が、子どもたちが群がるなかで、この絵本には近づくな! とガードしながら叫んでいるのも目撃しました。ニーズは読み通りでしたね。
――そこから現代美術での活動が開けたと。その後、東京藝術大学大学院に進み、2010年に伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞中編の部大賞を受賞。その脚本の映画化となる2011年の『惑星のささやき』はさまざまな映画祭で上映されています。その後、再び、2015年に伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞中編の部大賞。今回の『ひかりのたび』は、その脚本の映画化になります。
『ひかりのたび』も物語は5秒で思い浮かびました。ただ、植田奈々役に志田(彩良)さんに決まる前後で脚本は大幅に変更になりました。ひと言でいうと、当初は奈々の父親である不動産ブローカーの植田にクローズアップした内容でした。でも、それを不動産ブローカーの父と女子高生の娘をダブル主役にしたものへと変えました。この変更はプロデューサーと話し合ってのことだったのですが、当初、僕自身はそれで成り立つか半信半疑でした。女子高生と不動産ブローカーの話ではバランスのとりようがない。当然、みんな謎の多い不動産ブローカーに目がいきますから。でも、志田さんに出会って思ったんです。“バランスがとれるかも”と。具体的にいうと、志田彩良だから「彼氏が地元から出て行くのに地元に残る女子高生が描ける」と思えた。そして何よりも「不動産ブローカーの父の汚さを納得はしていないが理解している娘」を現実的に演じられそうな、本当に稀有な女優さんでした。志田さんの存在があって、今回の『ひかりのたび』になったといっていいです。
――表面的な部分だけなぞると、町を散々荒らしてこの地を去ろうとする不動産ブローカーの父と、それを重く受け止めこの町で生き続けることを決意する娘の切ない別れを描いたようにも思える。ただ、裏のテーマを紐解くと、外国人による土地の買い占め、村の有力者の覇権争いなど、ブラックな問題が浮かび上がります。
まず、「故郷を売る人間」と「故郷の喪失を恐れる人間」を描きたい気持ちがありました。僕自身は青森出身。ただ、もう青森より東京にいる時間が遥かに長い。地元で運転をすると地図はわらからないし、方言も忘れかけている。それでも、青森出身というのは自分のウリで、失いたくない要素です。また、現代美術において国籍表明は最重要必須項目。でも、それは村上隆や奈良美智のアニメテイストのように一見すると、“自国の文化の安売り”ととられかねない表現につながる。これらを現実社会の生活に近いところでキャラクターに投影させて両立させた物語にしたかった。あと、人間の命の価値を見極める者が、小さなアクションで世の中を大きく動かしていることについても言及したいと思いました。これも本作を作った大きな理由です。幸い、日本人は80年(人の一生分)近く戦争をしていない。それゆえ、このことをすっかり忘れて、口に出そうもんなら陰謀論と捉えかねない。
それを前提に、あくまでビジネスレベルでそれを実践している植田という人物を描きたかったところがあります。不動産という身近な職業をしているゆえ、誰でもその社会の仕組みがわかるものになったのではと思っています。なお、植田にはモデルがいます。バブル時代の不動産営業マンのバイブルであった『正しい「地上げ」のしかた・進めかた』『正しい「立ち退き」交渉の実務』の著者、植田六男さんです。彼が現代にいたら、“どういう仕事をするか”というのをイメージしたのも本作です。彼は、日本の合法型(非暴力)の不動産ブローカーの定型を作った人物といっていいです。
――今回のコンペのノミネートをどう受け止めていらっしゃいますか?
ノミネートの時点では素直にうれしかったです。ただその後、審査委員長が東京藝術大学大学院時代の恩師である黒沢清監督に決まったと聞き、その時点から複雑な心境に変わりました(苦笑)。黒沢さんは強烈な公平性の持ち主。そういう意味で、「SKIPシティアワード」のような自国の作家を優遇する制度などは、廃止を唱えてもおかしくないぐらい。でも、一方で教育者ですから、それだと日本の映画業界にいい影響がないことも認識している。また、自分の変えられない指向性を声高に公言して審査するというリスクも取れる人でもある。身内に囲まれたとしても、いわば敵の作品を平気で褒められる人でもあることを僕はよく知っています。それゆえに、今回の自分の作品がどういう評価をされるのかまったくわからないのがいますごく嫌です(笑)。あと、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭に関しては、日本の映像作家を冷酷に海外の作家と比べることができる数少ない映画祭だと思っています。僕ら作り手としては、次の作品作りへのビジョンが思い描きやすくなる貴重な場だと感じています。
――今後、目指すところは?
いまの映画は、あまりに真正面からやりすぎた作品ばかりで、ものすごい映画通か、もしくは話題になっているからとりあえずみてみようかという人しか観ないものになっている気がしてならない。観る層がすごく狭まっている。それ以外を呼び戻したい。濱口竜介監督はそれを演出面で実践しているけど、僕はそこに現代美術の考え方を取り入れて実践できないかなと思っています。あと、いまの映画やドラマのお金の描き方をみているとはっきりいって子どもだまし。大人のお金の流れをきちんと描いていない。変に汚くみせないようにして嘘をついたり、きれいなところに逃げ込む。それが団塊の世代をはじめとした上の世代にそっぽを向かれてしまう要因になっている気がする。そこは不動産やお金の汚いところを見てきた自分としては、逃げないで突き破った物語を作りたい。多くが人前では言わないけど、実は内心で信じていることやどす黒いかもしれないけど本心や真意を映画の中に入れ込んだある意味、正直な作品を発表していきたいです。
(文・写真:水上賢治)
・『三尺魂』 加藤悦生監督インタビュー
・『ひかりのたび』 澤田サンダー監督インタビュー
・『Noise』 松本優作監督インタビュー